 › 自然・山部会です › 2014年07月10日
› 自然・山部会です › 2014年07月10日2014年07月10日
やまやまにゅーす
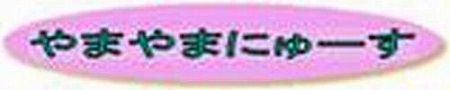
7月5日 割谷の路肩補修(3回目)
18人参加
前回作業をしたところのもう少し上、登る道を阻んでいた流木を除去し、
石畳風の道を付けました。
雨も予想されましたが、降らずに済みました。
歩く道がなかった沢沿いの所に道を作りました。
(画像をクリックすると大きく見られます)



割谷に向かう 割谷を登って 流木と土砂が堆積しているところ


流木と土砂を取り除く作業 流木を除去した跡に石の道
7月6日(日) 第2回森づくり塾開催
「間伐の仕方と道具の手入れ」
26人が参加し、県林業普及センターの職員さん3人が指導してくださいました。小堤の新林道近くの林で実習しました。


林業普及センターの職員さんの講義 伐採木にロープを架ける

見事に伐採、予定の方向に倒れました


専用の皮むきで皮を剥く 伐採木の皮むき完了。研修の成果


砥石でカマを研ぐ 欠けた刃をきれいに研ぎ戻す
4班に分かれて、ケガもなく無事終了できました、皆さんお疲れ様でした。
午前中はそれぞれ2本の間伐を体験。初めての実習でしたが班ごとのチームワークで無事終了。
午後は、ハサミやナタ・カマの研ぎ方の実習。山作業にとって一番大事な道具はこれからはもっと大事に手入れしながら作業を進めていきましょう。
❀ これからの予定❀
●7月15日(火)平日山作業
集合場所:貯木場 集合時間:9:00[午前中)
山部会の森整備=草刈・カブト虫の寝床整備
●7月26日(土)里山探索
集合場所:貯木場 集合時間9:00~15:00
小堤―吉祥寺山 (弁当もちで)
2014年07月10日
第2回森づくり塾 つづき1
午後からも新林道の真ん中で青空講習です。
空が少し曇ってきましたが、雨は全く降っておらず、
心地よい風が吹いていました・
山作業でよく使う道具の手入れについて学びました。
里山整備をすすめよう(道具の手入れ編)

発電機を使う自動研磨機で個人用の鉈を研いだり。

山作業をするとき、山仕事の道具はとても大事なものです。
道具がなければ仕事になりませんし、作業もなかなかはかどりません。
今回はその大事な道具の手入れについて学びました。
なたの研ぎ方の実習


鎌の研ぎ方講習


剪定ばさみの研ぎ方
剪定ばさみはよく使う道具ですが研ぎ方を知らなくて
ただ使うだけでしたがしっかり研いで
太目の枝を伐ってみるとパッキと伐れました。
これからはもっと道具を大事に使っていきたいものです。


研ぎ方の実習の中ごろから雨がポツポツ降り出してきました。
今日一日けがもなく安全に終了できました。
滋賀県林業普及センターの講師の皆様ありがとうございました。
講師の方の挨拶では、
やはり安全に講義が終了できて本当によかったというお言葉でした。
木を伐る、道具を扱う、山の中である、などいろいろな面を考えると
危険なことが多い事が多々あるところですが、無事終了できました。
森づくり塾受講生の皆さんお疲れ様でした。
山部会の山作業にはこの日の講義を今後も生かしていきましょう。
次回の森づくり塾は第3回
10月5日(日)郷土の歴史を学ぶです。
また元気にお会いしましょう(*^_^*)
空が少し曇ってきましたが、雨は全く降っておらず、
心地よい風が吹いていました・
山作業でよく使う道具の手入れについて学びました。
里山整備をすすめよう(道具の手入れ編)

発電機を使う自動研磨機で個人用の鉈を研いだり。

山作業をするとき、山仕事の道具はとても大事なものです。
道具がなければ仕事になりませんし、作業もなかなかはかどりません。
今回はその大事な道具の手入れについて学びました。
なたの研ぎ方の実習


鎌の研ぎ方講習


剪定ばさみの研ぎ方
剪定ばさみはよく使う道具ですが研ぎ方を知らなくて
ただ使うだけでしたがしっかり研いで
太目の枝を伐ってみるとパッキと伐れました。
これからはもっと道具を大事に使っていきたいものです。


研ぎ方の実習の中ごろから雨がポツポツ降り出してきました。
今日一日けがもなく安全に終了できました。
滋賀県林業普及センターの講師の皆様ありがとうございました。
講師の方の挨拶では、
やはり安全に講義が終了できて本当によかったというお言葉でした。
木を伐る、道具を扱う、山の中である、などいろいろな面を考えると
危険なことが多い事が多々あるところですが、無事終了できました。
森づくり塾受講生の皆さんお疲れ様でした。
山部会の山作業にはこの日の講義を今後も生かしていきましょう。
次回の森づくり塾は第3回
10月5日(日)郷土の歴史を学ぶです。
また元気にお会いしましょう(*^_^*)



