 › 自然・山部会です › 2015年06月
› 自然・山部会です › 2015年06月2015年06月26日
やまやまにゅーす
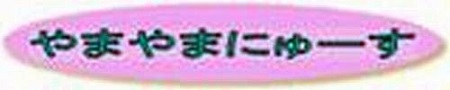
5月31日(日)第1回森づくり塾開催
「コンパスと地図で山歩き」
爽やかな緑の晴れの中、受講生32人が受講しました。
琵琶ドリームツアーの愛川・杉本講師の指導で、午前中は、コミセンしのはらでコンパスの使い方などの講義を受け、
午後は、野外のタムシバ山コースで実際にコンパスと地図で自分の行く方向を定めたり、現在位置を知る方法などやってみました。
なかなか難しかったけれど、宝の持ち腐れのコンパスの威力を知りました。


室内での講義 これから行く方向の設定

地図にコンパスをあわせて


表坂から新林道におりたところでグループごとに記念撮影
緑の部会と交流作業
6月16日(火)は、
山部会の方で城山の曲輪の整備を「緑の部会」とともに行いました。
山部会11人、緑の部会3人、両方所属4人の計18人が参加でした



城山郭の整備 左右の曲輪8段目 きれいなウラジロの葉
6月20日(土)に、
緑の部会の活動拠点「野洲川北流自然の森」の広大な草原の草刈りと、竹藪の新しく伸びた竹をたくさん伐りましたが、山とは違う草と竹との格闘の苦労を知りました。 マダケのタケノコもたくさんいただきました。休憩時間には、モロキュウやビワのごちそう。山部会員17人・緑の部会8人・両方に所属の6人、計31人の参加の盛況でした



竹藪の竹伐採 草刈りに奮闘 野洲川を望む


休憩時間 参加者記念撮影
7月4日(㈯)山作業のお知らせ
山部会の森の草刈りをします。
集合は貯木場に9:00
午後は同所で13:00から森づくり塾スタッフ会議
2015年06月17日
6月 平日山作業
6月16日(火)平日山作業の日でした。
野洲市の自然部会の仲間の「緑の部会」の皆さんが来てくださり
交流作業をしました。
「緑の部会」は市三宅で河畔林の再生事業やまちなかの
緑ボリュームアップ作戦をしておられます。
この日の作業場所は「小堤城山」へつづく曲輪址で、スギの樹林帯の
なかで一緒に汗を流して整備作業をしました。

以前は杉の枯れ枝が深く埋もれ、その上にウラジロ、ヒサカキやソヨゴ、
ツバキ、リョウブなどの低木が多く繁っていた所でしたが、今、ようやく人が立って作業できるようになりました。
【城山への登山道の左側にある郭跡の様子】

曲輪が右・左に多くありそれぞれに番号をつけて作業をしていますが
結構な斜面になっています。
【こちらは城山への登山道の右側にある郭跡の様子】

作業に来てくださった皆さんありがとうございました。
里山の斜面があるところでの作業でお疲れになられてのではないでしょうか。

次回6月20日は「緑の部会」の皆さんが活動されている市三宅の
野洲川北流跡堤防にお邪魔して交流作業をさせて頂きますので
よろしくお願いします。
野洲市の自然部会の仲間の「緑の部会」の皆さんが来てくださり
交流作業をしました。
「緑の部会」は市三宅で河畔林の再生事業やまちなかの
緑ボリュームアップ作戦をしておられます。
この日の作業場所は「小堤城山」へつづく曲輪址で、スギの樹林帯の
なかで一緒に汗を流して整備作業をしました。

以前は杉の枯れ枝が深く埋もれ、その上にウラジロ、ヒサカキやソヨゴ、
ツバキ、リョウブなどの低木が多く繁っていた所でしたが、今、ようやく人が立って作業できるようになりました。
【城山への登山道の左側にある郭跡の様子】

曲輪が右・左に多くありそれぞれに番号をつけて作業をしていますが
結構な斜面になっています。
【こちらは城山への登山道の右側にある郭跡の様子】

作業に来てくださった皆さんありがとうございました。
里山の斜面があるところでの作業でお疲れになられてのではないでしょうか。

次回6月20日は「緑の部会」の皆さんが活動されている市三宅の
野洲川北流跡堤防にお邪魔して交流作業をさせて頂きますので
よろしくお願いします。
タグ :里山整備作業、城跡整備曲輪跡
2015年06月07日
定例山作業 6月
6月の定例山作業で
城山曲輪(くるわ)跡の整備作業をしてきました。
新緑のウラジロ若葉がきれいです

曲輪はスギノキの樹林帯の中にあります。長い枝ごと落ちるスギノキが
積み重なって薄暗くなっていました。


クマデでかき集め地面が見えるところまで作業をしました。
ウラジロが繁っているところは下に何があるのかわからないほどでしたが石垣が見えてきました。




城山への登山道整備 ニガイチゴ タツナミソウ
午前中で作業が終わり山部会の森に移動して道具の手入れと小堤生産森林組合からお借りしている道具小屋の中の整理をしました


チェンソーの手入れ ノコギリの手入れ
午後からは森づくり塾スタッフが集まり、第二回森づくり塾講座の打合せ・役割分担などの話し合いをしました。
6月27日は山探索の日ですが、森づくり塾講座の予定地である「大笹原神社」の奥にある笹原を整備作業をすることになりましたので
よろしくお願いします。
午後も残れる方はお弁当もちで来てください。
蚊取り線香など蚊・虫よけ対策が必要です。
城山曲輪(くるわ)跡の整備作業をしてきました。
新緑のウラジロ若葉がきれいです

曲輪はスギノキの樹林帯の中にあります。長い枝ごと落ちるスギノキが
積み重なって薄暗くなっていました。


クマデでかき集め地面が見えるところまで作業をしました。
ウラジロが繁っているところは下に何があるのかわからないほどでしたが石垣が見えてきました。




城山への登山道整備 ニガイチゴ タツナミソウ
午前中で作業が終わり山部会の森に移動して道具の手入れと小堤生産森林組合からお借りしている道具小屋の中の整理をしました


チェンソーの手入れ ノコギリの手入れ
午後からは森づくり塾スタッフが集まり、第二回森づくり塾講座の打合せ・役割分担などの話し合いをしました。
6月27日は山探索の日ですが、森づくり塾講座の予定地である「大笹原神社」の奥にある笹原を整備作業をすることになりましたので
よろしくお願いします。
午後も残れる方はお弁当もちで来てください。
蚊取り線香など蚊・虫よけ対策が必要です。
2015年06月04日
森づくり塾・「タムシバ山」
「第1回森づくり塾」の様子を受講生の方がHPに
アップしてくださいました。
講座終了後、篠原駅近くから望む三上山のスケッチも
描かれています。

写真を豊富、文章もきれいにまとめてくださって
とてもうれしいです。
「低山歩きとスケッチ」
http://www.asahi-net.or.jp/~xr8k-tmr/
「里山散歩・タムシバ山」
http://www.ken-tmr.com/satoyamasanpo-yasu2015/satoyamasanpo.html
ぜひ田村さんのHPをご覧になってください。
アップしてくださいました。
講座終了後、篠原駅近くから望む三上山のスケッチも
描かれています。

写真を豊富、文章もきれいにまとめてくださって
とてもうれしいです。
「低山歩きとスケッチ」
http://www.asahi-net.or.jp/~xr8k-tmr/
「里山散歩・タムシバ山」
http://www.ken-tmr.com/satoyamasanpo-yasu2015/satoyamasanpo.html
ぜひ田村さんのHPをご覧になってください。
2015年06月03日
魚調査しました
5月27日(水)
希望ヶ丘の家棟川とJAカントリー近くの東祇王井川の2か所で
今年初めての魚調査をしました。
環境課からは投網をしてくださる方、NPO家棟川遊覧船の北出さん、
山部会からは3名参加しました。
最初の調査場所は新家棟川橋辺り
橋の下に入るとイワツバメの巣があり、驚いたツバメが10匹ほど高く低く飛び交い警戒している様子でした。

気温、水温、水深、草木の様子などや、生き物はどれくらいいるか数量の調査をしました。
投網3回でとれた魚を一匹づつ、体長、体重などの測定調査を行いました。

そのあとから希望ヶ丘へ移動して調査。
希望ヶ丘では元気よく泳ぐ魚がいっぱい目視できて魚影多しでした。
が、されど投網にはなかなか入ってきませんでした。

この日の魚の様子(小さい画像はクリックすると大きくなります)



① 3グラム ② 4,5cm ③ 5,5cm



④6cm ⑤7,5cm ⑥7,5cm



⑦7cm ⑧ 8cm ⑨8cm


⑩10cm ⑪10グラム
今まであまり深く考えなかった自然・風景・生態系ですが、魚調査をすることによって
学ぶことができて、とても良い体験をしました。
まだ体験されたことのない方はぜひいつか参加してみてください。
野洲市内を流れて、琵琶湖へと続くこの豊かな生態を
みんなで長く見守って行きましょう。
希望ヶ丘の家棟川とJAカントリー近くの東祇王井川の2か所で
今年初めての魚調査をしました。
環境課からは投網をしてくださる方、NPO家棟川遊覧船の北出さん、
山部会からは3名参加しました。
最初の調査場所は新家棟川橋辺り
橋の下に入るとイワツバメの巣があり、驚いたツバメが10匹ほど高く低く飛び交い警戒している様子でした。

気温、水温、水深、草木の様子などや、生き物はどれくらいいるか数量の調査をしました。
投網3回でとれた魚を一匹づつ、体長、体重などの測定調査を行いました。

そのあとから希望ヶ丘へ移動して調査。
希望ヶ丘では元気よく泳ぐ魚がいっぱい目視できて魚影多しでした。
が、されど投網にはなかなか入ってきませんでした。

この日の魚の様子(小さい画像はクリックすると大きくなります)



① 3グラム ② 4,5cm ③ 5,5cm



④6cm ⑤7,5cm ⑥7,5cm



⑦7cm ⑧ 8cm ⑨8cm


⑩10cm ⑪10グラム
今まであまり深く考えなかった自然・風景・生態系ですが、魚調査をすることによって
学ぶことができて、とても良い体験をしました。
まだ体験されたことのない方はぜひいつか参加してみてください。
野洲市内を流れて、琵琶湖へと続くこの豊かな生態を
みんなで長く見守って行きましょう。




