 › 自然・山部会です › 2013年12月
› 自然・山部会です › 2013年12月2013年12月19日
12月 平日山作業
山部会代表からの活動日程の報告です
12月17日(火)平日山作業は城山の登り道整備・ロープ張り
参加者は17名
大勢の方の参加があり整備作業がきっちり仕上がりました。
午後からは山作業終了後
城山から伊勢道峠入り口コースの下見。
前回の台風の風雨で、コースが荒れているところはないか点検。
倒木が多く10本ほど切りました。
修復が必要な場所は、大篠原側の道。
まだ10本ほどの倒木があるのと、
土砂が流されたり、イノシシに大きく掘られたところもありました。
修復の必要があるところが数か所あります。木を伐採したり、階段を作ったりなど資材の材木は、現地調達できます。
またタムシバ山花登山コースの下見の結果、
倒木や倒れそうな枯れ木が20本くらい有りそのうち10本くらい
は伐りました。
タムシバのツボミは、タムシバ山のところでは、たくさんついて
いました。
今年3月下旬のタムシバの花咲くころ

伊勢道峠からの登り道の急斜面が荒れていて階段を付ける、
木を伐るなどの作業が必要です。
階段づの木は、現地調達できそうです。カケヤ・
チエンソー・ツルハシ・ナタなどが必要です。
伊勢道峠越えも15か所ほどの土木工事が必要です。
1月11日(土)の山作業は、弁当もちで、15時ごろまですることにな りました。午後は都合の悪い方は、いつでも下山可能です。
山作業について
定例(第1土)・平日(第3火)の山作業は、原則、午前中の作業です。
ただし良いお天気の場合、午後も有志で軽い作業か山探索を2~3時間することもあります。その場合、時間の許す方は、お弁当を持ってきてください。
・第4土曜の山(里山)を知る探索の日は、お弁当もちで午後も3時頃までやります。
・参加される方は、マイカップ・マイお湯(できるだけ)(休憩時間にコーヒーなどを飲むためです)を持参してください。
12月17日(火)平日山作業は城山の登り道整備・ロープ張り
参加者は17名
大勢の方の参加があり整備作業がきっちり仕上がりました。
午後からは山作業終了後
城山から伊勢道峠入り口コースの下見。
前回の台風の風雨で、コースが荒れているところはないか点検。
倒木が多く10本ほど切りました。
修復が必要な場所は、大篠原側の道。
まだ10本ほどの倒木があるのと、
土砂が流されたり、イノシシに大きく掘られたところもありました。
修復の必要があるところが数か所あります。木を伐採したり、階段を作ったりなど資材の材木は、現地調達できます。
またタムシバ山花登山コースの下見の結果、
倒木や倒れそうな枯れ木が20本くらい有りそのうち10本くらい
は伐りました。
タムシバのツボミは、タムシバ山のところでは、たくさんついて
いました。
今年3月下旬のタムシバの花咲くころ

伊勢道峠からの登り道の急斜面が荒れていて階段を付ける、
木を伐るなどの作業が必要です。
階段づの木は、現地調達できそうです。カケヤ・
チエンソー・ツルハシ・ナタなどが必要です。
伊勢道峠越えも15か所ほどの土木工事が必要です。
1月11日(土)の山作業は、弁当もちで、15時ごろまですることにな りました。午後は都合の悪い方は、いつでも下山可能です。
山作業について
定例(第1土)・平日(第3火)の山作業は、原則、午前中の作業です。
ただし良いお天気の場合、午後も有志で軽い作業か山探索を2~3時間することもあります。その場合、時間の許す方は、お弁当を持ってきてください。
・第4土曜の山(里山)を知る探索の日は、お弁当もちで午後も3時頃までやります。
・参加される方は、マイカップ・マイお湯(できるだけ)(休憩時間にコーヒーなどを飲むためです)を持参してください。
Posted by ここあ at
09:31
│Comments(0)
2013年12月10日
12月の定例山作業
12月の定例山作業日
小堤にある城山城跡の草刈り作業に行ってきました。
作業前の蔓草におおわれている城址あたり




みんなでそろって作業中 朽ちた木の伐採 作業終了=きれいになりました

この日の参加者15名。ニコニコ笑顔で頑張って、寒さも吹き飛ばしてまったく元気です。


フジヅルをゲットしたHさんの笑顔 ヘビノボラズの赤い実
(つるかご作りが大好き) するどい刺がある(別名トリノボラズ)
午後からは城山から希望ヶ丘方面のコースの点検作業
(午後からも作業ができるという人と、
午後からの作業に来れるという人たち6人が参加しました)



台風被害の爪痕が多く見られ、小さな谷川も崩れていたり、
倒木もあちこちありました。
次回の山作業できるようにしるしをつけながら、点検してきました。
このあとの予定は
12月16日は山部会運営委員会。市役所別館1F午後5:30から
12月17日は「元旦の城山初日の出登山」ルートの整備作業
小堤にある城山城跡の草刈り作業に行ってきました。
作業前の蔓草におおわれている城址あたり
みんなでそろって作業中 朽ちた木の伐採 作業終了=きれいになりました
この日の参加者15名。ニコニコ笑顔で頑張って、寒さも吹き飛ばしてまったく元気です。

フジヅルをゲットしたHさんの笑顔 ヘビノボラズの赤い実
(つるかご作りが大好き) するどい刺がある(別名トリノボラズ)
午後からは城山から希望ヶ丘方面のコースの点検作業
(午後からも作業ができるという人と、
午後からの作業に来れるという人たち6人が参加しました)
台風被害の爪痕が多く見られ、小さな谷川も崩れていたり、
倒木もあちこちありました。
次回の山作業できるようにしるしをつけながら、点検してきました。
このあとの予定は
12月16日は山部会運営委員会。市役所別館1F午後5:30から
12月17日は「元旦の城山初日の出登山」ルートの整備作業
2013年12月04日
やまやまにゅーす
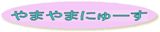
やまやまにゅーすはこのブログ用に編集して書いています。
11月の活動の報告
11月2日(土)
◎地元コミセンで行われる「収穫祭」のために出品する木の実や
松ぼっくり、ツルなどの採取。参加者8人。
◎また、おなじく11月23日に開催される山部会イベント「三上山」
登山のコース下見。参加者6人。
11月14日(木)
山辺の歴史の道づくり=第4回
銅鐸博物館~福林寺磨崖仏~野洲中辺りの古墳~円山
古墳。 参加者7人



古いお墓 福林寺磨崖仏 のどかな里山風景
11月16日(土)
兵主コミセン「収穫祭」に初めて
!!”山の店”!!出店
山部会のブースでは子供たちがミニクラフトづくりを楽しんでく
れてにぎやかでした。山部会参加者13人。

11月19日(火)平日山作業
城山登山道の道とロープの整備。急坂の傷んでいる道を
脇に付け替える作業。参加者15人


新しい道づくり作業 参加者
11月23日
「紅葉の三上山・東光寺登山」 アップダウンが続く健脚コース。
参加者22名
山々の紅葉がきれい


木の根と岩の険しい道を登る 山頂近くのビューポイントでしばし休憩
”今が一番の見事な紅葉満喫”
北尾根を縦走し妙光寺山から出世不動の分岐をおりて
日陽山東光寺出世不動明王 野洲不動尊へ

当面の活動予定
12月7日(土) 定例山作業 9:00城山館集合
12月16日(月) 山部会運営委員会
12月17日(火) 城山登山道のロープ整備 9:00城山館集合
12月18日(水) 山辺の歴史と自然散策コースづくり 13:00博物館集合
1月1日(元旦) 城山初日の出登山(小堤生産森林組合主催)
6:00城山館集合
1月11日(土) 山部会の森の整備・枯れ木伐採 9:00城山館集合
2013年12月02日
第4回森づくり塾2
夕日ヶ丘(向山)の古墳の様子
こんもりと丸い小山になっているところの様子から古墳とされていました。
樹木や土砂に埋もれています


4枚の大きな岩が並び、横にすこし隙間のあいている大きな古墳
すきまからのぞいてみると中はかなり広いようです

特別に許可をもらって中に入ってみると
大人一人手を広げてもまだあまるほど大きな内部でした。

見事に曲線を描いている須恵器の破片

ふるさと農道整備の時の発掘調査では(下の写真)=講義の時の画像
須恵器粘土が採掘された跡がみつかったそうです。

今はふるさと農道として車が行き交う道路を歩きながら
生き生きと暮らす人たちが住んでいたと思うと感慨深くなります。
地元野洲に住んで、地域の歴史を学び、知れば知るほど、ますます野洲が好きになったという人がふえました。
最後にふりかえりアンケートに書いてあったひと言!!
窯の火が夕日と競演したのか向山
秋晴れの山の紅葉目にしみる
里山を歩いて、新たな発見かな
こんもりと丸い小山になっているところの様子から古墳とされていました。
樹木や土砂に埋もれています


4枚の大きな岩が並び、横にすこし隙間のあいている大きな古墳
すきまからのぞいてみると中はかなり広いようです

特別に許可をもらって中に入ってみると
大人一人手を広げてもまだあまるほど大きな内部でした。

見事に曲線を描いている須恵器の破片

ふるさと農道整備の時の発掘調査では(下の写真)=講義の時の画像
須恵器粘土が採掘された跡がみつかったそうです。

今はふるさと農道として車が行き交う道路を歩きながら
生き生きと暮らす人たちが住んでいたと思うと感慨深くなります。
地元野洲に住んで、地域の歴史を学び、知れば知るほど、ますます野洲が好きになったという人がふえました。
最後にふりかえりアンケートに書いてあったひと言!!
窯の火が夕日と競演したのか向山
秋晴れの山の紅葉目にしみる
里山を歩いて、新たな発見かな
2013年12月02日
第4回森づくり塾1
12月1日(日)第4回の森づくり塾を開催しました。
今回の会場はいつもの城山館を変更してコミセンしのはらの研修室になりま
した。
野洲市環境課からは福山氏、サンケイ新聞を見てこられたF氏も来られて
26名の参加者。
年4回開催している「森づくり塾」も今回が最終の講座です。
今回は野洲市文化財保護課の福永清治氏をお迎えして地元「里山の歴史・
古墳探索」の講義。
午前中は映像を見ながらの講義で福永先生のわかりやすい解説に耳を傾けていました。

野洲の一地域にある小さなお山と言っては失礼なんですが「夕日ヶ丘」に眠れる(埋もれる)数々の古墳、土器の話に
徐々に興味深々となり、遠い昔・いにしえへと思いを巡らせ、いにしえ人がいきいきと生活している様を思い浮かべていました。
午後からは現地へ赴いての講義。
北風が吹く中、たんぼ道からふるさと農道を横切って山麓へ。


土器を作っていた窯跡について 夕日ヶ丘登山口から向山に登る

夕日ヶ丘(向山)の全景写真(講義の映像より)


夕日ヶ丘古墳群、穴蔵古墳群には1号から21号までの古墳があり、近年の新幹線工事で須恵器など多くの土器が見つかっている。

また戦国時代の向山城の縄張り図面を見ながら現地確認作業。
虎口跡もあり、古墳を櫓台として使われていた可能性もあるとのこと。人々の生きざまを伺いしることができました。
NEXTあり
しばらくお待ちくださいm(__)m
今回の会場はいつもの城山館を変更してコミセンしのはらの研修室になりま
した。
野洲市環境課からは福山氏、サンケイ新聞を見てこられたF氏も来られて
26名の参加者。
年4回開催している「森づくり塾」も今回が最終の講座です。
今回は野洲市文化財保護課の福永清治氏をお迎えして地元「里山の歴史・
古墳探索」の講義。
午前中は映像を見ながらの講義で福永先生のわかりやすい解説に耳を傾けていました。

野洲の一地域にある小さなお山と言っては失礼なんですが「夕日ヶ丘」に眠れる(埋もれる)数々の古墳、土器の話に
徐々に興味深々となり、遠い昔・いにしえへと思いを巡らせ、いにしえ人がいきいきと生活している様を思い浮かべていました。
午後からは現地へ赴いての講義。
北風が吹く中、たんぼ道からふるさと農道を横切って山麓へ。


土器を作っていた窯跡について 夕日ヶ丘登山口から向山に登る

夕日ヶ丘(向山)の全景写真(講義の映像より)


夕日ヶ丘古墳群、穴蔵古墳群には1号から21号までの古墳があり、近年の新幹線工事で須恵器など多くの土器が見つかっている。

また戦国時代の向山城の縄張り図面を見ながら現地確認作業。
虎口跡もあり、古墳を櫓台として使われていた可能性もあるとのこと。人々の生きざまを伺いしることができました。
NEXTあり
しばらくお待ちくださいm(__)m



